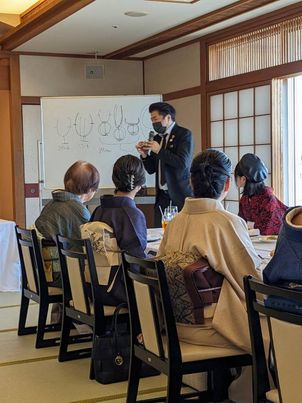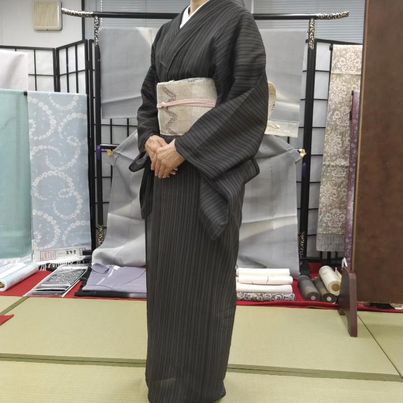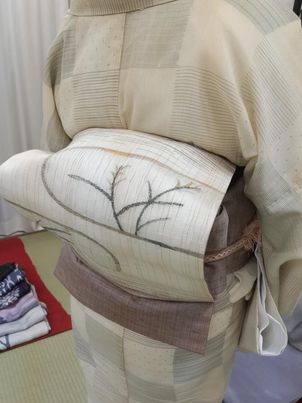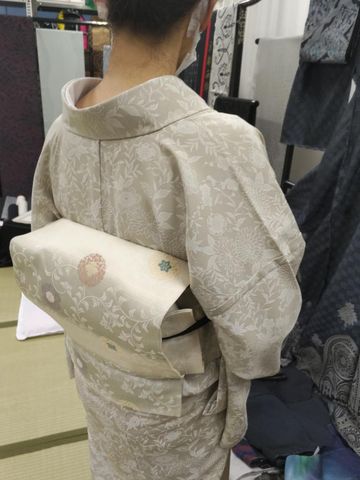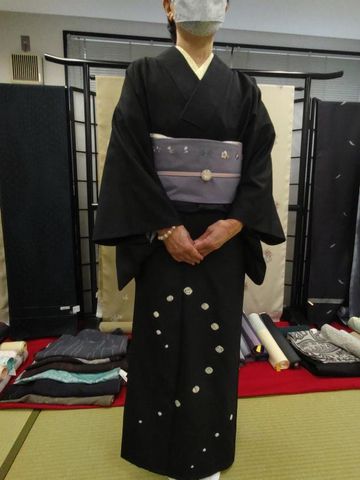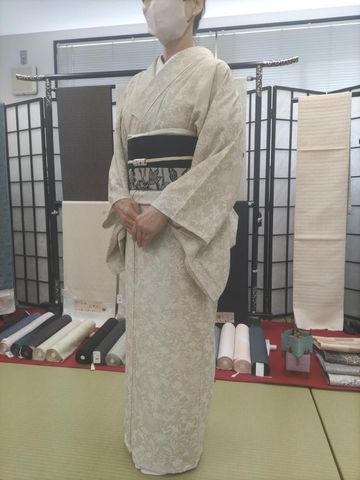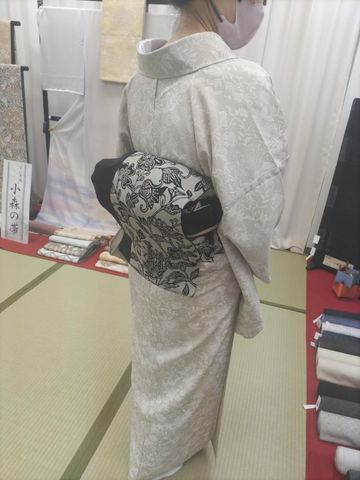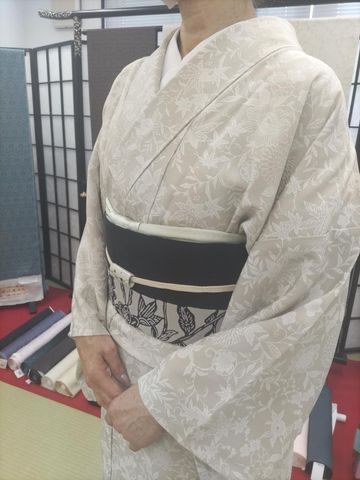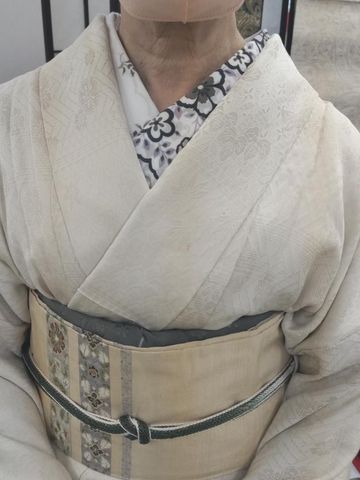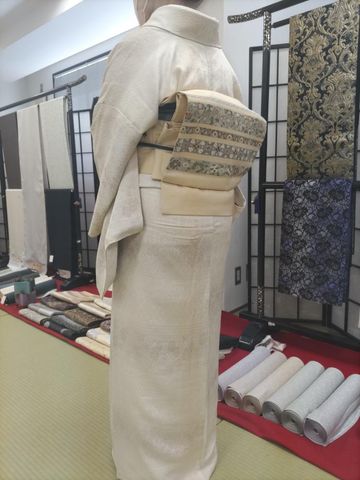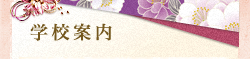年に一度、テーブルマナー講師を行っております。
昨年は、洋食のコース料理の講習でしたので、今年は季節の和食懐石料理をいただきながらの講習でした。
先ずは、食前酒(果実酢)をいただき前菜三種とお箸の扱いから。



お造りの盛り合わせの食べる順番や、小鍋、お肉料理、揚げ物。
そして、御飯と味噌汁(留め椀)
味噌汁は、鎌倉時代に中国から日本へ来た僧がすり鉢で、豆味噌をすりつぶし
水に溶かしたところから、味噌汁として食されるようになりました。


味噌汁の丁寧に表現した言葉が御御御付(おみおつけ)
室町時代から宮中での言葉だそうです。
豆も粗く、御飯のおかずとして食べていたという説もあるそうです。
このような、雑学知識も教えていただきながら楽しい講習でした。


和食は私達が、日常的に食べている料理なのにいざ懐石料理となると
作法が難しかったり、知らないことも多いものです。
お箸や小鉢一つの扱い方も知っておけば所作も美しく見えます。
まして着物であれば所作が美しいと一層、着物姿も映えるのではないでしょうか。
今後も学院の生徒さんでなくても、一般参加も大歓迎です。
お持ちのお着物を着る機会の一つとして
次回は、是非貴女もご参加下さい。

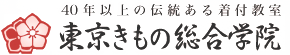

















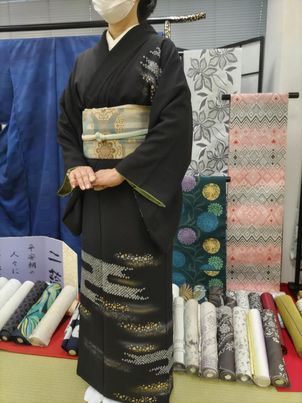




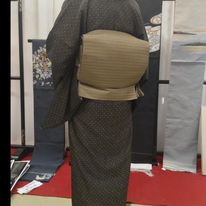















 この度はお声掛けありがとうございました😊
この度はお声掛けありがとうございました😊